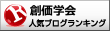「坊主丸儲け」という諺がありますが、この言葉は江戸時代の浮世草子(風俗小説)のなかの『風流茶人気質』に、「魚三層倍、呉服五層倍、花八層倍、薬九層倍、坊主丸儲け」と書かれているのが発祥だと言われています。魚屋は原価の3倍、呉服屋5倍、花屋8倍、薬屋は9倍の利益があり坊主(僧侶)は原価がないかなら全部は儲けになるから「丸儲け」というわけで坊主の後に「按摩掴み取り」なんて言ったりします。どちらかというと皮肉的な意味合いで使われることが多いですが、今風に言えば坊主(僧侶)は不労収入といったところでしょうか。しかも宗教法人は非課税なので「丸儲け」っぽく思えますよね。でも本当に坊主は丸儲けなのでしょうか?私は「そうじゃない」と思います。目に見える部分で言えば寺院の人件費や維持費・修繕費などそれなりにコストはかかります。でも一番元手(原価)がかかっているのは目に見えない部分です。昔の僧侶は庶民と比べると知識も豊富で信徒に色々な事を教える役目をしてきました。そうした知識には「仕入原価」というものはありませんから傍から見ると「丸儲け」のように見えますが、「知識」を得るためには時間とお金がかかるのです。私も法華講や創価学会員の友人に仏教関係の質問をされますがたまに冗談で「30分1万円だぞ」と言います。まぁ30分1万円はボッタくり過ぎますが、私自身が仏法を学ぶためにこれまで費やしてきた時間や購入した書籍などを考えれば無料で教えてくれと要求する方がボッタくりです(笑)。僧侶の法話も無料で手に入れたわけでありません。僧侶が「丸儲け」なら教師だって「丸儲け」です。もっとも今の時代は知識はスマホで検索すればすぐに入手できます。しかし僧侶は信徒や一般人が絶対に手に入らないモノを持っています。それは「徳性」です。その「徳」を得るために日蓮正宗では少年得度の場合は小学校を卒業すると総本山に登り修行を積むのです。一番遊びたい盛りの思春期に仏道修行するなんて一般人にはとても耐えられない。その修行に耐えた僧侶の「徳性」は計り知れません。知識を得るだけならネットで十分ですが僧侶の法話と違って功徳にはなりません。このような功徳の対価として寺院や僧侶に供養や布施を払うのです。もちろん他宗派においても宗派なりの修行を積んで僧侶になっているわけです。従って「坊主丸儲け」と思うのは僧侶に対して失礼だし心根が卑しいと感じます。本当に丸儲けしているのは、修行もせず僧侶でもなく、宗教学者でもなくて知識も徳政も無いのに寄付や献金を受け取っている創価等のカルト宗教団体の職員たちです。これらの宗教団体・職員こそ「丸儲け」なのです。だってそれは宗教詐欺なのですから。こういうカルト教団が跋扈しているから人々が宗教を敬遠し日本人から宗教心を奪い日本文化が破壊されていくのだろうと思います。また伝統宗教の僧侶はもっと頑張って布教するべきだと思いますよ。カルト教団の連中に「坊主丸儲け」なんて言われて余裕をくれて笑っている場合じゃないのでは?
創価学会の退会方法(静かに創価を去るために) - 創価ダメだしブログ
▼一日「イチ押し」お願いします