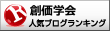「理数系」とよく言われますが、学生時代の私は数学は好きで得意だったけど「理系」は苦手で成績が特に悪いわけではないけどなんか面白くないし興味が持てませんせした。特に「物理」は全然ダメで授業が退屈で憂鬱でした。男子は実験好きが多いと聞くけど実験も興味なしでした。それでも大人になってからニュートンなどを読んでみました。アインシュタインの『相対性理論』の関する書籍も数冊読みましたが半分も理解してません。なにせ一番面白かったのが『名言集』ですから(笑)。分かったような分からないような『相対性理論』ですが、『相対性理論』は『特殊相対性理論』と『一般相対性理論』の二つの別々に書かれた理論の総称です。普通は『特殊』の方が難しいと思うけど後から書かれた『一般相対性理論』の方が難しい。『特殊』は特別な条件下(具体的には重力の影響を受けないという条件)での相対性理論です。【E=mc2】 の世界一有名な数式は物質がエネルギーに変換される時の公式で『特殊相対性理論』から導き出されたものです。仏教的に言うと肉体は滅んでも消滅するのではなくエネルギーに変わり、逆にエネルギーは何かのきっかけで物質になるということで、仏教の生命観に通じますね。またニュートン理論の時間や空間は変化せず絶対的な存在である(絶対空間・絶対時間)というそれまでの物理学の常識を覆し、時間や空間は『相対的な存在』であるという理論を打ち立てたのが『相対性理論』です。ニュートンは「1秒は誰にとっても同じ1秒」であるという主張でしたが、アインシュタインは時間は光速に近づくほど遅くなるので時間は不変ではなく、また空間も伸縮するので絶対時間・絶対空間は存在しないと結論しました。またニュートンは時間と空間は別々な存在と位置づけていましたが、アインシュタインは時間と空間は密接に関係しているとして「時空」という概念を創造しました。今では普通に「時空」と言う言葉を使いますがそれもアインシュタインの『相対性理論』に基づいています。『相対性理論』の時空の捉え方も仏教の『空』の思想に通じるし、観察者によって時空が変化するのは『唯識』にも通じます。もっとも物理学は自然現象の原理・法則を追求する学問であり、人間の生命や幸不幸の原理・法則を追求する仏教と同じといえます。仏の法理のことも【仏理(ぶつり)】といいますから呼び方も同じです。多くの人が物理と仏教の共通点を感じ論じていることも納得です。その反面で宗教は非科学的と否定的な主張をする人もいますが、天才・一流と言われる科学者や数学者の多くは科学や数学の世界は宗教的世界に繋がっている事を体感しています。無信仰者と言われているアインシュタインも「すべての宗教、芸術、科学は、同じ一つの木の枝である。」「無限なものは二つあります宇宙と人間です前者については確信できませんが」「宗教なき科学は不自由であり科学なき宗教は盲目である。」「近代科学の必要に応じることができる宗教があるとすれば、それは仏教であろう。」等の言葉を残しています。ともかく仏法を学んでからは物理も面白いと思うようになれたのはひとつ自分の中の収穫です。(といってもやっぱり物理の数式は苦手です)学生時代にこの面白さを知っていたら物理の成績がもう少し良かったかも知れないと思うと自分が残念です(笑)。
▼一日「イチオシ」お願いします
Image may be NSFW.
Clik here to view.
にほんブログ村