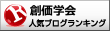浄土真宗の信徒を揶揄する言葉に「門徒もの知らず」というものがある。この言葉は「門徒もの知らず、法華骨なし、禅宗銭なし、浄土情なし」という地口・洒落の一部だ。今風に分かりやすく言うと門徒(真宗)は無知。法華(日蓮宗)は根性無し。禅宗は貧乏。浄土宗は薄情。ということになるだろうか。浄土真宗は念仏しか知らない、頼らないという意味で「門徒はもの知らず」と言われる。専修念仏の宗派なのだからそれはそれで他宗派がとやかくいう事ではないが(専修念仏が正しいわけはない)、数ある仏教宗派の中でも先祖への追善供養をしないなど真宗は他宗や世間から見れば仏教の行儀を知らない(もの知らず)ように見えるのも無理はない。何故、真宗(浄土宗も)が先祖回向しないかというと、浄土系では念仏を唱えれば死者は外れくじなしで全員もれなく極楽浄土に生まれて仏になるので既に仏である(成仏した)先祖に追善回向する必要がないからだ。ところが不思議なことに真宗でも彼岸会・盂蘭盆会の法要をしている。無論、追善供養の意味合いではなく極楽浄土を願ったり先祖の恩に報いるという意義があるらしいが生前に一度でも念仏唱えれば(真宗の場合は念仏を唱えずとも)阿弥陀如来を信じるだけで成仏確定なのだから真宗の寺院にわざわざ参詣する必要もないし、寺院で彼岸会・盂蘭盆会の法要を行う意味もない。当然だが総本山・本願寺を始めとする真宗寺院ではこうした矛盾を理由を付けてはそれが祖師・親鸞上人の教えだと言っているが本当にそうだろうか?生前に「自分が死んだら遺骸は魚に与えよ」とまで言っていた親鸞上人が彼岸会とか盂蘭盆の教えを説くとは考えられない。そのような教えを説いた遺文が存在するのか知らないが私が読んだ親鸞上人の書物には書いてなかったと思う。そもそも本願寺は第三世・覚如が『改邪抄』を顕し親鸞上人の教えの正統を護り第7代・存如まで信徒が集まらず停滞していた。同じ真宗でも先祖供養や年忌法要・彼岸を執り行っていた本願寺以外の真宗寺院が参詣者で溢れて栄えていたことのだから本願寺衰退の大きな理由が先祖供養や年忌法要を重視しなかったことにあると言っていいだろう。そんな本願寺を改革したのは第8代・蓮如だ。蓮如はそれまでの本願寺の保守的な体質を改めて言葉は悪いかもしれないが大衆に迎合することによって本願寺を復興させたのである。それは親鸞上人の教えを歪曲したと言えなくもない。つまり現在真宗寺院で行われている彼岸や盂蘭盆の法要は真宗の祖師である親鸞上人の正統な教えではないということであり親鸞上人や総本山・本覚寺の第三世・覚如に敵対する行為であるといえよう。親鸞上人が大聖人のように唯授一人血脈相承をしていたら本願寺は日蓮正宗のように現在でも祖師の正統を貫いていたかもしれないと思うと親鸞上人が少し気の毒な気がしないでもない。それにしても『門徒もの知らず』をいいことに親鸞上人を利用して信徒を誑かせているのは身延日蓮宗や創価学会同様に浄土真宗もえげつない。そういえば本願寺派門主が現代版聖典を作りその内容がそれまでの教義と違うといって騒ぎになったがその後どうなったのだろう?もっとも前述の如くとっくの昔に浄土真宗は親鸞上人の教義とは違ってしまっていると思うから今さら教義云々なんてどうでもいいのでないかと思う。教義論争というか門外漢の私には宗内の権力闘争にみえる。真宗は絶対他力なんだから教義なんてどうでもいいのではないだろうか。
■関連記事▶有名僧侶略伝⑤親鸞 - 創価ダメだしブログ
▼一日「イチ押し」お願いします