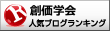SNSで創価学会員らしき人物が「大聖人本仏論の根拠である末法は最近の研究では1600年前後の安土桃山時代とされているので大聖人が本仏という根拠はない」とう疑難を持ち出しているこを知ったが学会員が大聖人本仏を否定する様は憐れみを感じる。もっとも私も末法論の疑難は過去に何度か受けたことがある。日蓮正宗の教義と仏教に無知ゆえの論理だが反論を書いてみる。現在では釈迦は紀元前500年前後の人物であるというのが通説で、それに従って末法を滅後2000年説に当てはめると確かに末法は西暦1500年前後になり鎌倉時代ではない。しかし摩耶経などに説かれる末法は滅後1500年説に従えば紀元1000年前後辺りから末法ということになりこれは平安後期から鎌倉前期に当たる。当時の日本においては末法は1052年から始まると考えられていた。それは釈尊の入滅を中国説の紀元前949年として末法2000年説を用いたからで当時の日本人にとってはそれが定説だった。日本で最初の説話集の『日本霊異記』や藤原資房の『春記』などに末法の到来と書かれていて当時の和歌にも末法を意識した釈教歌も多く詠まれている。摩耶経を引用している御書もあるので大聖人は末法1500年説も当然知っていただろうが当時の定説に即して説法したと思われる。このように末法の始まりの時期は経典によって違っていて時間軸では正確な末法の時期は定義はできない。各教典共通の末法の定義は釈迦仏法が効力を失う時を末法ということである。日本の仏教史をみれば『大集経』の説く『闘諍言訟・白法隠没』(釈迦仏法が効力を失う時)が始まった時代は平安後期から鎌倉前期であることは明白で大聖人御在世の時代は末法の時にあたるのである。そもそも大聖人本仏論とは大聖人を「本因妙の御本仏」「久遠元初の御本仏」と立てることなので、「末法の」というのは「釈迦仏法の末法」と言っているに過ぎず、それは釈仏法に即した教相・外用の表現でしかない。従って「いつから末法になったのか?」などという議論は従であり傍の議論で、そのような本質から離れた枝葉末節の理論で日蓮大聖人御本仏論を否定するのは日蓮大聖人の仏法を分かっていない門外漢の戯言に過ぎない。もちろん門外漢に日蓮大聖人の仏法を理解しろとは言わないが、学びもしなければ教えも請わず知ったかぶりして否定・批判するのは恥かしいことだ。そもそも学術的な事実と宗教的事実は異なるのが信仰の世界である。創世記や古事記などの神話は科学的には正しくないがキリスト教や神道を信仰する者にとっては神話の解釈を含めて事実なのである。学術的アプローチで信仰学を批判・否定する人は多いが宗教を語る(批判)うえで知性が不足している。歴史的・科学的な事実のみを信じるのは自由だがそのような人間は宗教・信仰の分野に立ち入る必要はない。もっとも人間の考える学問が全てを解明し常に正しいという立証はされていないから学問で宗教を否定するのは不可能である。それは一流の頭脳を持つ多くの科学者達が信仰を持っていたり宗教を肯定していた事実からも明らかだろう。いずれにしても「末法」を時間軸だけで捉えるのは仏教的には稚拙な理論なのである。
★創価・顕正からの退会・正宗への移籍・創価破折方法の相談はX(Twitter)のDM、メール(sokadamedasi@gmail.com)、でお気軽に。※正宗への勧誘目的ではありません。(可能なら当ブログのコメント欄に「メール送った」とコメントしてください)
▼一日「イチオシ」お願いします