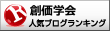先日アメリさんから、【先日、眷属から『大聖人様は法華経以外の教えは仮の教えであると主張したのに、なぜ立正安国論には法華経以外の経典を引用して三災七難の警鐘をしているのですか?』と聞かれました。体内体外の法門について取り上げてくださるとありがたいです!】とのご質問をいただきました。日蓮大聖人が破折しているはずの爾前経を御書で引用している理由は、日寛上人が『立正安国論愚記』のなかで、「問う、既に未顕真実という、何ぞまた爾前を引用せんや」との問いを設けて4つの理由を御指南されています。①「爾前はこれ法華の為の網目なる故に」爾前経は法華経の大綱を説明するための部分的な綱目の教えであるから。②「文は爾前に在るも義は法華に在るが故に」文字(言葉)としては爾前経にあるけど本義は法華経にあるから。③「爾前の劣を以て法華の勝を況する故に」爾前経が法華経に劣っていることを示すため。④「爾前の文を借りて法華の義を顕すが故に」爾前経の言葉を借りて(付文)法華経の実義を表すため。という理由によって権教(爾前経)を引用しているのです。このうち③は「相待(妙)」、①②④は「絶待(妙)」の立場になります。「絶待妙」といのは不完全な教え(爾前経等)を完全な教え(法華経)に会入することで、それにより爾前は全てが法華経の一部となり相対する経はなくなることになります。この「絶待妙」の立場から説かれた爾前経を「体内」といい、「相待妙」の立場から見た爾前経を「体外」といいます。つまり法華経に一度流入してそこから再び説かれる(開会)れたのが「体内」で、法華経に合されずに単独に説かれている教えを「体外」というわけです。法華経の開経の『無量義経』に「無量義とは一法より生ず」と書かれていますが、この「一法」が絶待妙で爾前経以外にも外典の教えであっても全て法華経を説明するための綱目となるわけです。ただし法華経を「絶待妙」とすることは釈迦仏法に準ずる文上・教相の天台大師教学で、日蓮大聖人の文底下種仏法に約せば法華経もまた「相待妙」となります。大聖人仏法における「絶待妙」とは、「南無妙法蓮華経(戒壇大御本尊)」に他なりません。従って大聖人が御書の中で爾前経や時には外典の言葉を引用されるのは、「南無妙法蓮華経」の法体を所持されている御本仏の立場から・・つまり「絶待妙」の立場から爾前・外典を開会・会通されているからです。また大聖人仏法を知らない人達に分かりやすく説明するための「法用方便」ともいえます。折伏相手に応じて様々な方便を用いて折伏する大聖人の化導方法は現在の我々の折伏にも通じます。大聖人仏法の法門法義以外の仏教知識や一般教養を身に着けることが大切です。そして大聖人仏法以外の事を学ぶ時は常に「絶待妙」の立場で学んでいくことが肝要です。
★創価・顕正からの退会・正宗への移籍・創価破折方法の相談はX(Twitter)のDM、メール(sokadamedasi@gmail.com)、でお気軽に。※正宗への勧誘目的ではありません。(可能なら当ブログのコメント欄に「メール送った」とコメントしてください)
▼一日「イチオシ」お願いします