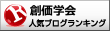以前、落語の記事を書きましたが実は落語は仏教から生まれたって知ってましたか?最初の落語家は秀吉の御伽衆として仕えた曽呂利新左衛門(そろりしんざえもん)と言われています。曽呂利は刀の鞘を作る腕利きの職人で彼の作った鞘に刀を差すと「そろり」と入ったことから曽呂利と呼ばれるようになったそうです。彼を架空の人物とだという説もありますが彼にまつわるエピソードは数多く残っていてその真相は分かりません。落語としての起源は江戸時代(1623年)に作られた『醒酔笑』という笑い話を集めた作品集だと言われています。『醒酔笑』は現代でも現代語訳版の書籍が販売されています。『醒酔笑』は古典落語に大きく影響を与え、【子褒め】や【たらちね】のネタ元になっています。「ざーくざくのばーりばり・・ちんちろりんのさーくさく」という有名なセリフがある落語が「たらちね」です。この『醒酔笑』の作者が安楽庵策伝が【落語の祖】と呼ばれています。策伝は安楽庵流という茶道の祖ですが、戦国時代から江戸時代にかけて活躍した浄土宗西山深草派の「説教僧」でのあります。「説教僧」というのは仏教の経典や教義を分かりやすく楽しく講釈して人々を教化する僧侶のことです。当時はこのような説教僧が各宗派にいたのですね。つまり落語は仏教の「説教」「法話」から生まれた文化・芸能が「落語」なのです。現在の伝統仏教の寺院は説法もあまりしないし聞きに行く人も少ない。そもそも伝統仏教各宗派の僧俗は遠慮しているのか面倒くさいのか分かりませんが布教を積極的にしないので「説法」も葬儀や法事の時くらいしかません。そんな中、僧俗ともに積極的に布教をしているのは唯一日蓮正宗だけなのですが、布教をしている日蓮正宗を他の宗派は批判したりしますが私からしたら布教もしない僧侶の方がどうかしていると思います。そんなだから創価などの新興カルト宗教に信徒を取られひいては社会を不安と混乱にさせているのです。伝統仏教宗派には少しは反省して欲しいものです。さて布教をしている法華講員はいわば「説教僧」のようなものですから、一人一人が落語家になって新作落語を創るような気持ちで、聞く相手が仏教に興味を持ち楽しくなるような話をするようにしたいですね。そのような話ができるようになるために仏教の知識は当然ですが、仏教以外の知識も勉強してそしてたまには落語を聞いて話術の練習をしましょうか(笑い)

■関連記事▶落語から学ぶ弘教のテクニック【文化・芸能】 - 創価ダメだしブログ
▼一日「イチ押し」お願いします