日本人の美意識のひとつに『わびさび』という心がありますが、皆さんは『わびさび』と聞いて何を思い浮かべますか?利休の「茶の湯」・芭蕉の「俳句」・雪舟の「水墨画」など様々でしょうが、『わびさび』って何かと訊かれても具体的に説明できませんが、私が考える『わびさび』は月に譬えると、「満月」は風流、「新月」は幽玄、そして「三日月・弦月」が『わびさび』です。また『わび』は相対的で『さび』は絶対的というイメージを持っています。『わびさび』を一文字で表すならば、【不】です。「不足」「不備」「不自由」などなど。そうした「不完全」な状態に物事の無常を感じる一方で、その無常の中に「不朽」「不滅」の美しさを見てることが私は日本人の「わびさびの心」ではないかと思うわけです。海外にも、ルソーなどのバルビゾン派の絵画やジャズ音楽などに『わびさび』を見て取れるのですが、やはり少し違います。ルソーと雪舟の絵を比べると、ルソーの絵は完成しているけど雪舟の絵は未完成の完成なんですね(これは明治維新前の日本絵画全般的にそうです)。芭蕉の句も華やかさは一切なく自然のままです。そういう意味では利休はちょっと’あざとい’。利休の有名なエピソードで次のような話があります。【利休の庭に朝顔が見事に咲き誇っているという評判を当時の天下人である豊臣秀吉が聞きつけ利休の家に見に来ることなります。ところが秀吉が来る当日の朝、利休は庭の朝顔の花をすべて摘み取ってしまいました。庭を訪れた秀吉はその状況が飲み込めません。不思議に思ったまま茶室に入ると、そこには、「一輪の朝顔」が生けられていた。】という話なんですが、これは人工的な『わびさび』です。そもそも、利休自身が何不自由のない暮らしをしていたいわば裕福層であり権力者ですから利休の「わび茶」はブルジョワジーが創作した『わびさび』でどこか不自然さを感じます。確かに茶道は『わびさび』の世界なのですが、高額な茶器や軸などが本当に『わびさび』なのかは疑問を感じます。さて、そんな日本人の『わびさびの美学』はどこから生まれたのかと考えるとやはり日本人の宗教観だろうと思います。特に仏教思想が日本人の『わびさびの心』を育んできた事は【空観・中観】に通じる『わびさび』の精神に明かです。日本人が歴史ある神社仏閣に『わびさび』を感じるのは、伽藍が古いという建物だけでなく、その空間全体から感じ取るのだと思います。しかし、最近のインバウンドによるオーバーツーリズムで、京都・奈良・鎌倉を始めとする全国の神社仏閣や歴史ある場所に『わびさび』など理解できない外国人が溢れかえっています。この状況は日本人の精神文化の破壊であり精神の売国行為であると思います。またこうした惨状を招き放置している政治に対しても憤りを感じる人も多いのはないでしょうか。現代日本は戦後教育の影響もあり共産主義的唯物論が蔓延しているのがこうした現状を生み出している原因のひとつだと思われ、新興宗教団体も宗教とは名ばかりでその実は共産主義的唯物論に立脚している。多くの日本人は、神道・仏教を問わず日本古来の伝統宗教への回帰をする時期に差し掛かっていると感じます。
▼一日「イチ押し」お願いします
Image may be NSFW.
Clik here to view.
にほんブログ村
Image may be NSFW.
Clik here to view.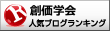
創価学会ランキング
